2017年発表の新品種・「よつぼし」を使うことで家庭菜園でも12~5月まで収穫することを目指すページです。
家庭菜園でのやり方だけ見たい方は、このページの【家庭菜園でも、促成栽培と同じく半年間収穫しつづける方法】まで飛ばしてください。
他の部分は、どうして当サイトでそのような育て方をしているのか、管理人の思い付き主観は入れず「試験データ」「プロ農家の育て方」といった根拠もとに書いています。それを、家庭菜園の様な小規模でも、出来る限り安価に真似できるような工夫を書いています。

【従来品種と同じ育て方】

「よつぼし」に限らない、普通のイチゴと同じ栽培方法です。★株管理、★増殖・育苗 がこの栽培方法でだけかかる手間です。
苗をいちど買えば、翌年・よくよく年・・・とランナー増殖した苗をそのまま使えるのでもう買う必要がないです。一見節約になっていますが・・。
★株管理は、休眠期のイチゴに少し水を与えればいいのですが、スペースをいっちょ前に取ります。
★増殖・育苗 が問題でして、いっちょ前のスペースのいちごを夏越しさせないといけません。冷却・遮光の方法を用意しないといけません。(これは育苗ポットに紙ポット採用+底面給水+いつもの1.3~1.5倍の肥料施肥で改善できますが)。それとなにより高温時期には多い病害虫です。この手間が普通のイチゴ品種では問題になりますよね。そしてランナーをうまい事発生させないといけませんし(低温要求時間は満たせますが、花芽分化条件とほぼ同じ条件をクリアさせないと発生しない)、そのランナーから病気が遺伝することも多いので油断できません。
実はこの手間を一切カットする方法があります。それが次から紹介する、「よつぼし」ならではの育て方です。
【二次育苗】※よつぼし栽培で普及してる方法

7月に「セル苗」を購入し、ポットでまず育苗(2次育苗とよぶ)し、9月に植え付ける方法です。
※セル苗=超小型で沢山の苗が集まったもの。苗1個のサイズは406穴が最も小さく(下記図)、70穴が最も大きいサイズ。

苗を全部購入することになるので苗代がかかり、その苗も育苗してから植付の手間がかかります。
ですが、ランナー生殖させずに済むので病気の遺伝・ランナー発生の失敗・真夏の暑さ対策は無縁となります。実はよつぼしのメリットはこれです。
【本圃直接定植】※よつぼし栽培で普及してる方法

いちばんシンプルかつ低リスクの方法です。セル苗(殆ど406穴セル苗でしょう)を直接本圃に植付け、「花芽誘導」をし(8月下旬の2週間窒素中断 又は 9月下旬の2週間長日処理)、12月ごろから温室モードにして収穫する方法です。
2次育苗とおなじく苗代がかかります(406穴セル苗で42000円など)。しかし、よけいな手間が一切ありません。夏越しなども無い為、場所もとりません。
メリット➡➡育苗~定植までの作業時間が「従来の栽培方法」とくらべて実に90.3%(!)も低減する、画期的な栽培方法です。

参考:三重農研成果報告より引用
参考:種子繁殖型イチゴ品種「よつぼし」の栽培技術体系より引用
【生産者が播種から行う】 ※よつぼし栽培で新出の方法

先ほどのセル苗よりも単価の安いよつぼし種子を購入し、播種~鉢上げまでもが生産者が行う方法です。
メリットは、種子代はセル苗代よりも安い事。
デメリットは播種してから発芽・育苗するまで自分でやるので技術が必要・手間も必要です。
【本圃直接定植でランナー利用】 ※よつぼし栽培での新出の方法

基本的には本圃直接定植と同じです。違うのはセル苗の購入数を半分にし、そのぶん苗どうしの間隔を(通常30㎝の倍である)60㎝にする点と。もう一つ違うのが定植時期が一週間早い事(ランナーを出させるため)。
メリットは本圃直接定植と同じで、苗育成・播種などの施設が一切要らないこと。
デメリットはランナーが万一出なかった場合に、収量が減る事。
【上記5つの方法で、どれが最優秀なのか?】
「本圃直接定植」とされています(外部リンク)。
その為、当サイトでも「よつぼしの本圃直接定植」を推奨します。
【最優秀とされる「よつぼし本圃直接定植」の詳細な方法】

よつぼしの商業用の栽培方法で最も優れているとされる「本圃直接定植」は、もちろん促成栽培の一つです。(半促成栽培、露地栽培、抑制栽培いずれでもない)
その具体的な方法はこちらです。最新の促成栽培方法をベースにプラスして、よつぼしならではの工夫が必要になります。

■■よつぼしの花芽分化条件と一年の気候(美濃加茂の例)■■
| 0~ 5℃ | 5~ 10℃ | 10~ 15℃ | 15~ 20℃ | 20~ 25℃ | 24.8~ 28.2℃ | 28.2℃~ |
| 休眠 | 無条件で 花芽分化 | 短日条件で 花芽分化 | 短日条件で 花芽分化 | 短日条件で 花芽分化 | 長日条件で 花芽分化 | 花芽分化 しない |
| 真冬の露地と同じ 休眠 | 12月・3月の気候 殆ど生育しない | 11月頃の気候 あまり生育しない | 10月頃の気候 生育しやすい | 9月頃の気候 4月頃も遮光すればOK 生育には最適 | 5~6月の気候 地面温度25℃超は生育鈍る | 7~8月の気候 この温度帯はダメ |
+さらなる条件として「クラウン直径8㎜以上」「葉っぱ枚数13枚以上」(=幼苗期を脱したくらいの成長度。外部リンクのp4のグラフ参照)が必要。
よつぼしのメリットは、24.8~28.2℃の時に長日条件で花芽分化(外部リンクのp5参照)出来る事。5月6月の日本の気候そのまんまので、あまり手をかけずともこの気温をキープでき有難い。ただし花芽分化できても、生育し易い気温ではない(地面温度25℃超すと成長が鈍りだす)ので注意したい。
【家庭菜園ではどの作型が向くのか?】
ずいぶん規模の小さい話しになりますが。家庭菜園でも同じことが言えます。
| ●栽培方法● | ●総評● |
| 従来品種 と同じ栽培方法 | 苗代はゼロ。 しかしいちご親株の夏越しが必要。 病害虫に感染しやすく、素人では判別もし難い |
| 二次育苗 | 家庭菜園むけの小規模セル苗が存在せず、不可。 セル苗は70苗が最小だが、家庭菜園でそんなに不要。 |
| 本圃直接定植 | 小規模セル苗はないが、代りに9号ポット入りの 十分大きい苗を買って直接本圃(プランター)に植えられる。 (9号サイズと大きい為、そもそも二次育苗が不要) 定植までに手間も技術も要らない唯一の方法。 欠点はホムセンで早いところでも9月上旬まで売られない事 |
| 生産者が 播種から行う | 種子代が15粒で1000円からと高価。 素人が播種・発芽・定植までするので技術必要。 しかも病害虫感染リスクあり。 |
| 本圃直接 ランナー利用 | 本圃直接より早い時期に、苗が出回ってないので不可。 ランナー増殖させるにも技術必要。 |
家庭菜園やるときも、同じく「本圃直接定植」が第一候補となります。もちろん「土と植木鉢が予備で有る」「夏越しはクーラーの効く部屋で・かつ南向き窓際にスペースを確保できる」のなら、従来品種と同じランナー生殖させての栽培方法も可能です。ですが病害虫が感染するリスクありますよね。
やはり毎年、よつぼしの苗を買って定植するのが無難な様に思います。
【家庭菜園でも、促成栽培のように収穫しつづける方法】
「家庭菜園で(本圃直接定植と出来るだけ同じ)促成栽培」ともなると、工夫が必要です。費用もスペースも限られるので、(1苗当りの費用は高くついても)できるかぎり総計で安く、知識もいらず、他と兼用できる道具をフル活用して、作る必要があります。
<ビニールハウス>
(骨格+ビニールのセット。耐荷重が15Kgあるのが唯一無二。650型プランターもすっぽり置けるサイズ。)
<ビニールハウス外張り>
二重温室化するため必要に。
案1)透明ごみ袋+発泡スチロール案。これは「透明ごみ袋」などの空袋を代用して、切り貼りして作ればOK.元々のビニールハウスとの間に空気層を作るため、発泡スチロールを噛ませるのがポイント。専門のモノを買うまでもなく、不用品で自作すればただで作れるし探す手間も要らない。
➡これもかなり安価だが、管理人不採用。
案2)プチプチシート案。プチプチシートはそれだけで空気層を持っているので、これを切り貼りしてビニールハウスに貼りつけるだけでよい。
➡管理人採用。プチプチ部分が常に空気層なので断熱性抜群のため。これも安価にできる


※プチプチ袋は、長さ240㎝×縦90㎝くらいあれば650型プランター2鉢+αくらい覆えるので十分。なお管理人は、車のバンパー包んでたプチプチシートを流用した(むかしキャラバンのバンパーをぶつけて、自分で修理するさい購入したもの)。
※贅沢いうなら耐久性がある糸入り透明シートを使いたい。
<650型プランター>
一般的な650型プランターの定番品。土は最大14Lまで入る。白色は光をはじき、デコボコは表面積が多くなるので夏場の昇温抑制に役立つ。
<デュポンタイベック 700AG>
本来は「デュポンタイベック 700AG」がいいが家庭菜園用の小分けはない。その為単価は高いが同性能をもつこれで代用する(住宅用だが曲げに強く、湿気のこもる家の壁でも30年耐久するすぐれもの)。これをプランターまわりにぐるりと一周まく。下には空気が通る余裕をつけること。
<イチゴ栽培の培地>
650型プランター+鉢底石+イチゴの培養土12L とするのが家庭菜園では無難。
650型プランター+14Lのアクアフォーム+消石灰14g とし、何度も水を流してもOK。(管理人はアクアフォームをブルーベリー栽培の為沢山持っており、こちらを採用)

まず650型プランターを用意。中に14L(山盛り位)のアクアフォームを入れ、14gの消石灰を投入。ここに水を大量に流すことで洗う。

いちごを両端と真ん中の3カ所に植え付ける事ができる。

いちごの培地にはマルチングを忘れずに。写真ではフェルトでマルチングしているが、水を通すものなら何でも使える。敷き藁が一般的。
・・・ここからは、冬特有の保温の準備について。
<植物用ヒーターマット>
2500円以下と安価なのに防水問題なし。床から植物プランターを温める。(注意)屋外でのコンセント使用が必要に!
・・・もし屋外コンセントが使えない場合、安全にできうるのは「毎朝と毎夕に熱湯入れた2Lペットボトルを、温室内に入れる」くらいしかない。(ベランダや庭で石油ストーブ使うのは、一酸化炭素中毒や火災の危険があるのでダメ) 毎日メンドウになるが、毎朝4L沸かして2Lはハウスへ直接いれ、もう2Lは保温ケトルに入れて夕方に入れる様にすればいい。ぬるくなった湯は水やりに使える。
・・・ここからは、夏特有の冷却の準備について。
<デュポンタイベック スリムホワイト60>

プロ農家が使う物と全く同じもの(=つまり大きさの割に安価・高性能・高耐久)。2m幅なので、3mで切ればレジャーでも大活躍するサイズに。このサイズは家庭菜園の小規模イチゴプランターなら十分護れる。オーニングとしても耐久性・熱の持たなさは市販品と段違いの高性能で優秀。白黒のストライプは、案外シンプルでカッコイイ。
注:購入時に必ずハトメ加工をしてもらう。風にあおられることを想定する為。また農業用ではないけど、屋外レジャーでのタープとしても使いやすくなる。
家庭菜園のような小規模では送風による温度低下まではねらえず、真夏の収量が落ちてしまう事が考えられる。
もしくは・・・いっそのこと6月にはエアコンの効いた室内に取り込んでしまう。家庭菜園の小規模であれば現実的。
以上が、用意するものリストになります。

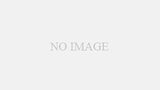
コメント