ベランダでも家庭菜園を諦める必要はないです。
というか、ベランダならではのメリットも沢山あるので、ベランダでいちごを作れます。
うまく活かすと、1月~7月まで連続収穫も出来てしまいます(実際私が収穫しています)。連続収穫している、私のやり方を公開します。
【いちごベランダ菜園で使う物】
| いちご苗(よつぼし) | 9苗 | |
| 650型プランター | 3個 | |
| 650型プランター受け皿 | 3個 | |
| アクアフォーム | 100L入り1個 | |
| 100L入り1個 |
【ベランダいちごの日ごとの変化】
2023年10月:
いちごを4株(らくなりいちご2株・よつぼし2株)を定植しました。
プランターは650型クイーンプランターで、いちごを定植します(ホントは3苗ずつ定植可能)。2プランター作りました。

奥は3苗(らくなり×2、よつぼし×1) 手前はよつぼし1苗定植
その後、らくなりいちごが枯れたので抜いています。
2023年11月:
いちごを4株追加です(よつぼし×4株)。
ミニ温室を購入しました。これは冬でも5度以上をキープして、冬でもいちご収穫をするためでした。

二段式ミニ温室 幅69×奥行49×高さ92

いちご650型プランター 2つ入れる
よつぼしからランナーが出ました。ランナーを埋めることで、1株増えました。

ランナー発生 下のピンクポットで受けて増殖
2023年12月
よるは外気温5℃を切ってしまうので、温室は締め切り、熱湯ペットボトルとペットヒーター(サーモスタットにより)で温めています。

サーモスタット(15℃以下で電源ON、20℃以上で電源OFF設定)
なおヒーターは「屋外電源コード」で電源をとり、「サーモスタット」をはさんだ先に「ペット用ヒーター100W」をつけています。
サーモスタットの設定は寒い時だけ加温する・熱くなったら加温なし とします。夜間は7℃を切ったら加温開始・12℃を超えたら加温なし、昼間は15℃を切ったら加温開始・20℃を超えたら加温なし。夜間は光合成しないので、多少寒くても大丈夫なのです。

(左下)屋外電源コード、(上)サーモスタット、(右下)ペット用ヒーター
いちご(よつぼし)に花が咲きました。花が咲くと、その40日後くらいで収穫できます。外気温0℃前後なのでいちごは休眠するはずですが、ここは温室内の為休眠せず成長し続けています。

12月15日 真冬なのにいちご開花!
2024年1月
真冬なのによつぼし収穫できました。

1月にして収穫を待つイチゴ
2024年2月
ハダニ(ナミハダニ)が発生。しかも蜘蛛の巣状になっているので発見遅すぎました。

ハダニが湧いて蜘蛛の巣状になった葉っぱ
このままではいちごが弱るので、農薬を購入しました。
●ダニ太郎(ビフェナゼート)
●カダンプラスDX(エマメクチン)
●ベニカマイルドスプレー(デンプン糖化物液)
ベニカマイルドスプレーは「無制限に使える・耐性化しない」ので何度もつかいますが、残留性がない。だから残留性があるダニ太郎・カダンプラスDXを交互に使います(交互なのは耐性化する為です)。
具体的には「ベニカマイルド(無制限)➡ダニ太郎(回数制限あり)➡ベニカマイルド➡カダンプラス➡ベニカマイルド・・・」の順番で使っています。
2024年5月
花が沢山つくだけでなく、ランナーの数も増えました。そのためか小苗も沢山採れています。ランナーを受けるのは「セリアの8㎝紙ポット(16個入)」で、土もセリアの100円培養土を使います。もしくはアクアフォームでもかまいません。
紙ポットを使う理由:水が染み出すので、気化熱で苗が冷えてくれるからです。いちごは暑すぎると花芽分化してくれないので、気化熱があるだけで―7℃くらいされて(検証済み)好都合です。さらには紙の分解する際窒素を消費し、低窒素でますます花芽分化しやすくなります。

セリアの8㎝紙ポット16個入り コスパ最強
毎日見ているのでハダニで蜘蛛の巣というのはありません。6月になるとハダニが殆ど発生しなくなりました。
2024年6月
ハダニはたまごをみかけますが、動く虫は殆どなくたまごも「ダニ太郎」で殺卵しているので大丈夫です。葉っぱのチェックは週1回で済むようになりました。
いちごのミニ温室を改良し、1段の高さを31.5㎝➡50㎝にUPさせました。やり方はDAISOの「突っ張り棒 115㎝~190㎝ 太さ16㎜/13㎜」を買ってきて、外の16㎜パイプを50㎝ずつにカットしただけです。写真の白い棒が50㎝パイプ。

DAISO200円突っ張り棒115㎝~190㎝の外側を利用

縦パイプ(黒色)の長さ31.5㎝ 狭い!

白い50㎝パイプに交換

縦パイプを50㎝(白色)につけかえ 広々!

2段とも縦パイプを50㎝(白色)に変更 使いやすい!
高くなったおかげで下のプランタにも光が差し、農薬や肥料もずいぶんあげやすくなりました(水やりは電動ポンプで自動化しているので不要です)。
ふつうイチゴの時期は終わっていますが、我が家では6月末でも収穫が続きました。これは品種を「よつぼし」にしたため、春だけでなく夏も花芽分化が続いたためと思います。あとは屋根がある関係上昼間の直射日光が当たらないため、暑さに強くなっていた為です。
2024年6月26日
6月下旬だというのに新たな花房が付いて、この通り花と実が沢山あります。

2024/6/26 夏なのに花房・実が沢山

2024/6/26いちご棚の様子
2024年7月8日
管理人の居住地は7月に入り最高気温32~37℃、最低気温21~23℃となっています。いちご苗も日なたに近い部分は夕方、水分を失ってぐったりしています。しかし(苗でない部分の)プランターのイチゴ株殆ど元気で、この日も収穫できました。

イチゴの実が沢山ついてます
ただ収穫できる株にある法則をみつけました。
・・・これ以外にも、「いちごプランターは軒下に置くことで、真夏の昼間の直射日光は当たらないが朝晩の日光は当たる」「いちごプランター0を軒下におくことで、雨や泥がイチゴに当たらない」「いちごプランターはベランダに置くので、風が凄く通る」という工夫を全プランターにしています。この全てが揃った株は、1月あたま~7月8日までずっと花芽が付き続け、ずっと収穫できているのです。
おそらく「不織布マルチがいい」のは水やりの気化熱でイチゴが冷え、「ベランダ底面にあてない」のは灼熱のベランダ熱気が当たらない、のが理由だと思います。
さらに面白いのは、花芽がつかない「不織布マルチをしていないプランター」は、ランナーが次々と発生していることです。このことから花芽にいくはずの栄養が、ランナーとして出て行っていると思われます。
2024年7月10日


ランナー苗を定植
7株のうち1株枯れていたので抜きます。おそらくこの数日の高温(33℃➡37.7℃➡34℃➡35℃と経過)でやられました。でもランナー苗のバックアップが沢山あるため、それを植えました。
何とこの日もイチゴ収穫。しかも3個。
ランナー苗はここで取っています。真ん中の棚のイチゴは実がつかない分、余った栄養がランナーにいくので沢山苗が取れています。

真ん中棚のイチゴ(左側) 実がつかずランナーばかり 右側はラベンダー
これで我が家のいちごは、1月10日~7月10日まで半年間、なりつづけたことになります。やや甘味おちたかなくらいで、今でも美味しいです。

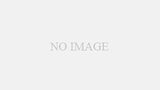

コメント